- 更新
- 10月・11月・12月
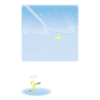
喪中ハガキで思い出すのは祖父が亡くなったときのこと。祖父が亡くなったのは、11月。なんとか、相手方が年賀状の用意を始める前に喪中はがきを出すことが出来ました。
あの時、「おじいちゃんが亡くなったのが、12月だったら…」と家族で話しました。
喪中はがきを出す時期は、11月から12月上旬とされていますが、年末おしせまる12月に不幸があった場合は喪中はがきの時期っていつなのでしょう?
あと、弔事用切手をご存知ですか? 私は最近、知りました。
スポンサーリンク
喪中はがきの時期 年末に不幸があった場合
まさに、年末。年もおしせまる年末の時期に不幸があった場合、喪中はがきは、いつ出せばいいのでしょう。そもそも、出すべきでしょうか?
喪中はがきは出さずに、寒中見舞いはがきを出しましょう。
喪中はがきは、「今年は年賀状を出すことを控えさせていただきます」という年賀欠礼をお詫びする挨拶状。相手からの年賀状の受け取りが禁止されているわけではありません。
しかし、喪中はがきを受け取ったら年賀状を出すのを控えるのが一般的。
そのため、喪中はがきは、相手が年賀状の準備を始める前の11月から12月上旬までに届くようにするのが望ましいとされています。そこで、年末に不幸があった場合。
この場合には、喪中はがきは出しません。松の内(1月7日)が明けてから、寒中見舞いはがきを出しましょう。連絡が遅れたお詫びとして寒中見舞いを出すのが一般的。
その際に、年賀状をいただいたことへのお礼と、喪中のため、年始のご挨拶を差し控えさせていただいたことのお詫びの言葉を書き添えます。
喪中はがきの時期 12月の初旬に不幸があった場合。
では、年末ではなく12月の初旬や、11月の下旬頃に不幸があった場合は? ポイントは、喪中はがきを出した場合に12月15日までに届くかどうかです。
12月15日までに届くなら、喪中はがきを出すのもありとする意見を考える
12月15日までに届くなら喪中はがきを出すとする意見があります。理由としては、郵便局の年賀状受付が始まるのが、12月15日からのため。
それまでに喪中はがきが届けば、相手が年賀状の投函をしなくてすむから。とする意見。
これは、おすすめしません。寒中見舞いにすべきと思います。
あるアンケートによれば、9割の方が「年賀状の投函は、12月16日以降にする」と答えています。確かに、12月15日までに喪中はがきが届けば年賀状の投函は止めれるでしょう。しかし、相手方はすでに年賀状を準備している場合も多いはず。
喪中はがきは、相手が年賀状の準備を始める前に届くように出すものですから、この形はおすすめできません。(禁止されているわけではありません)
年賀状の準備を始める前とすれば、遅くとも、12月の初旬には喪中であることを伝えておくべきと考えます。相手の迷惑にならないためにも、12月の初旬に不幸があった場合にも、年末に不幸があった場合と同じく、寒中見舞いで対応するのが良いと考えます。
スポンサーリンク
弔事用切手とは?
祖父が亡くなった時の喪中はがきは、近所のスーパーのサービスカウンターで印刷の申込みをしたと記憶しています。なので、切手を貼った覚えはありません。
最近、弔事用切手というものがあることを知りました。
弔事用切手
喪中はがきは、デザインに決まりがあるわけではなく、はがきを購入して自作したり、自宅で印刷して作成するなどしても問題ないとされます。白黒やカラー、背景に蓮や睡蓮などの絵が入っているものなど、お好みで作成してみるのも良いかもしれません。
私製はがきで作成する場合は、仏事の案内に使用する弔事用の切手を使用します。弔事用切手は郵便局の窓口で購入することができます。
最近では、弔事用切手を必ず使わなければいけないという事はないため、通常の切手を使用しても、問題はありません。
喪中はがきの時期 年末に不幸があった場合のまとめ
喪中はがきは、こちらから年賀状を出さないことを伝えるもの。相手からの年賀状を受け取ることになっても問題ない。なので、慌てて喪中はがきを出す必要はない。
松の内が明けてから、寒中見舞いはがきを出すのが妥当。年賀状へのお礼の言葉、喪中のために、年始のご挨拶を差し控えたことへのお詫びの言葉などを書き添える。
喪中はがきを自作してみても良いかも。切手を貼る場合は、弔事用切手を使用する。ただし、絶対ではない。最近では、通常の切手で代用してもかまわないとされる。
スポンサーリンク










