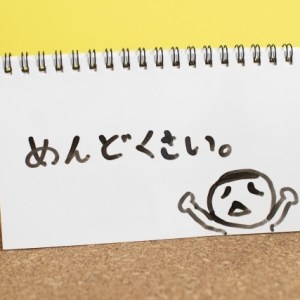- 投稿
- 生活

長年、勤めてきた会社を退職となれば、
ホッと安心する安堵の気持ちと、
想いは、人それぞれだと思います。
そして退職と共に
「退職金」というものがあります。
実際、「退職金」の存在は知っていても、
退職金にかかる税金はいくら払えばいいのか、
算出の仕方について具体的には知らない方がほとんどだと思います。
そこで、今回は
退職金3000万円にかかる税金はいくらなのか、
翌年の税金はどうなるのか、
退職金にかかる税金の計算の仕方を含め、
お話したいと思います。
スポンサーリンク
退職金3000万円にかかる税金はいくら?
まず始めに、課税対象になる退職金の計算の仕方を
ご紹介したいと思います。
課税対象になる退職金の金額=(収入金額-退職所得控除)×1/2
次に退職金所得控除の計算方法についてですが
勤続年数20年以下なのか20年超えているのかによって
計算式が変わってきます。
[勤続年数20年以下の場合]
40万円×勤続年数
[勤続年数20年超えの場合]
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
これらを基に計算します。
ここで、例として勤続年数30年で3000万円の退職金の場合の
計算をしてみましょう。
勤続年数が30年ということは、
20年超えているので二つ目の計算式に当てはめます。
となり、1500万円までは
税金がかからないということになります。
そして課税対象になる金額は
ということになります。
ここで、注意したいことがあります。
「退職所得申告書」を事前に、会社へ提出しておけばよいのですが、「退職所得申告書」を提出していない場合、退職所得控除を受けることができず、退職金のすべてが課税対象にになってしまいます。
その場合、源泉徴収を行うため、
退職金の20.42%を税金として払うことになります。
先ほどの退職金3000万円の場合で計算すると
3000万円×20.42=612.6万円が徴収されることになるので、
当然、手取り金額も少なくなります。
そのため、「退職所得申告書」は忘れず、
事前に会社へ提出しておくのが賢明ですね。
スポンサーリンク
退職金を受け取った次の年の税金の注意点とは?

退職金を受け取ってホッとするのも束の間…
次の年の税金にも関係してくるので注意が必要です。
そもそも住民税というのは、所得に応じて支払いますが、
退職した月と住民税を計算する月には、
期間にずれがあることを念頭においておきましょう。
住民税に関して、平成30年度は
平成30年6月~平成31年5月までが対象となります。
もし9月に退職した場合、
対象の残り期間である10月~翌年5月に納めるべき納付書が
年末の12月に届きます。
しかし、納付金額については
前年の平成29年1月1日~12月31日の所得を基に
計算されていることを覚えておきましょう。
よって、平成31年度の住民税に関しては、
平成30年1月1日~退職までの期間を基に
納付金額が計算されるので、退職するまでに
この支払いを念頭において別で蓄えておくとよいと思います。
退職金の税金の計算についてのまとめ

退職金の税金の計算について書いてきましたが、
いかがでしたか?
長い間、勤め上げた会社を退職する際の退職金。
せっかく受け取っても、税金の支払いで
驚くことも少なくないと思います。
そして翌年まで…となると大変ですよね。
「その時」が近づいてきたら、
事前に調べて、予め計算しておくことで
いざ支払うときにも困らないで済みますね。
そして退職した後は、自分の時間を大切にして、
趣味などに人生を謳歌して頂きたいと思います。
スポンサーリンク